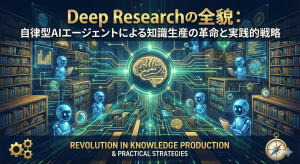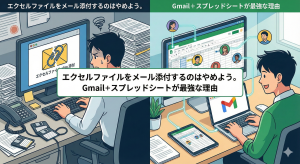2025年5月27日、第19回デジタル社会推進会議幹事会において、政府は「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」を策定しました。このガイドラインは、急速に発展するAI技術を行政分野で安全かつ効果的に活用するための包括的な指針として、令和8年度以降の政府情報システムに全面適用されます。
G7広島AIプロセス等の国際的な動向を踏まえ、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の一環として策定された本ガイドラインは、行政の進化と革新を目指すとともに、利活用促進とリスク管理の両立を図る画期的な取り組みです。本記事では、ガイドラインの主要なポイントを詳しく解説し、関係者が実務で活用するための具体的な指針をお伝えします。
1. ガイドライン策定の背景と意義
AI技術の急速な発展と国際的な動向を踏まえた政府の戦略的対応
策定の背景
-
AI技術の急速な発展ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、官民問わずAI活用のニーズが急激に高まっています。特に行政分野では、業務効率化や住民サービス向上への期待が大きく膨らんでいます。
-
G7広島AIプロセス等の国際的な動向G7広島サミットで合意されたAIに関する国際的な枠組みや、各国政府のAI戦略を踏まえ、日本政府としても統一的な指針の必要性が高まりました。
-
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」における位置づけ政府のデジタル化戦略の中核として、AI活用による行政サービスの質的向上と効率化が重要な柱として位置づけられています。
-
各府省庁での生成AI活用検討の進展各省庁で個別にAI活用の検討が進む中、統一的なガイドラインによる品質確保とリスク管理の必要性が明確になりました。
2. ガイドラインの基本情報
適用対象、範囲、実施時期などの基本的な枠組み
位置付けと適用対象
位置付け
デジタル社会推進標準ガイドライン群(DS-920)として、政府情報システムにおける生成AI活用の規範文書として機能します。法的拘束力を持つ重要な指針です。
対象システム
テキスト生成AIを構成要素とする政府情報システムが対象です。ただし、特定秘密、秘密、機微情報を扱うシステムは除外されます。
対象AI
大規模言語モデル(LLM)を構成要素とするテキスト生成AIが主な対象です。画像・動画等の生成AIは今後の検討対象となっています。
対象者
AI統括責任者(CAIO)、企画者、開発者、提供者、利用者(政府職員)など、AI活用に関わる全ての関係者が対象となります。
適用開始時期
-
令和8年度以降:全面適用令和8年度(2026年度)以降の調達・利活用から、本ガイドラインが全面的に適用されます。
-
令和7年度:可能な範囲で実施令和7年度(2025年度)は準備期間として、可能な範囲でガイドラインに沿った取り組みを実施します。
-
独立行政法人・地方公共団体への期待独立行政法人や地方公共団体に対しても、本ガイドラインへの準拠・参考が期待されています。
3. 政府における生成AIの利活用方針
積極的な活用推進とリスク管理の両立を目指す基本方針
基本的な利活用方針
積極的な業務活用検討
各府省庁に対して、生成AIの積極的な業務活用を検討するよう呼びかけています。単なる効率化だけでなく、行政サービスの質的向上を目指します。
AIガバナンス強化
便益とリスクを適切に理解し、リスクに応じた適切な対策を実施することで、安全で効果的なAI活用を実現します。
段階的な実装アプローチ
低リスク業務での迅速な実装から始め、経験を積みながら高リスク業務への挑戦を支援する段階的なアプローチを採用します。
「高リスクな生成AI利活用」の考え方
-
リスク軸による判定利用者の範囲・種別、業務の性格、要機密情報・個人情報の学習有無、出力結果の人間による判断有無の4つの軸でリスクを評価します。
-
高リスク判定シート(別紙1)の活用具体的なリスクレベルを簡易に判定できるツールとして、高リスク判定シートが提供されています。
-
リスクに応じた対策の実施判定されたリスクレベルに応じて、適切な技術的・組織的対策を講じることが求められます。
4. AI利活用促進とガバナンス強化のための体制構築
政府全体と各府省庁における推進体制の整備
政府全体の体制
各府省庁の体制
5. 生成AIによる便益とリスクの理解
期待される効果と想定されるリスクの包括的な整理
期待される便益
- 行政目的の効率的・効果的な実現(文案作成、要約、翻訳等)
- 企画立案能力、情報収集・分析能力の向上
- 政策・文書・分析等の質の向上
- 既存システムの機能・利便性向上
- 住民サービスの24時間対応・多言語対応
- 職員の創造的業務への集中促進
- 行政コストの削減と効率化
想定されるリスク
- 技術的リスク:データ汚染、バイアス、ハルシネーション等
- 社会的リスク:個人情報漏洩、生命・財産への影響、知的財産権侵害
- 政府特有のリスク:政治的中立性の確保、説明責任の履行
- 運用リスク:ベンダーロックイン、システム依存
- セキュリティリスク:情報流出、不正アクセス
- 品質リスク:誤情報生成、不適切な出力
リスク対策の基本的考え方
-
予防的対策の実施リスクが顕在化する前に、技術的・組織的対策を講じることで、安全な運用を確保します。
-
継続的な監視・改善運用開始後も継続的にリスクを監視し、必要に応じて対策を見直し・強化します。
-
透明性の確保AI活用の目的、方法、リスク対策について、適切な説明責任を果たします。
6. 政府における生成AIの調達・利活用ルール
各主体の役割と責任、導入類型に応じた対応
導入類型に応じた対応
A: 規約同意型
既存のクラウドサービス型生成AIを利用規約に同意して利用する形態。比較的低リスクで迅速な導入が可能です。
B: 個別契約型(開発なし)
既存サービスを個別契約で利用する形態。カスタマイズや追加的なセキュリティ対策が可能です。
C: 個別契約型(開発あり)
新規開発を伴う形態。最も高度なカスタマイズが可能ですが、開発・運用コストとリスクが高くなります。
各主体の対応事項
生成AIシステム特有のリスクケースへの対応
-
差別的出力への対応性別、年齢、国籍等に基づく差別的な出力が発生した場合の迅速な対応手順を整備します。
-
危険コンテンツ生成への対応暴力的、違法な内容の生成を防止し、発生時の適切な対処を行います。
-
ハルシネーションによる不利益への対応事実と異なる情報の生成による被害を最小化するための対策を講じます。
7. 実務に役立つ!付属チェックシート・ひな形の紹介
ガイドライン実装を支援する具体的なツール群
提供される支援ツール
チェックシート活用のポイント
段階的な活用
企画段階では高リスク判定シートでリスク評価を行い、調達段階では調達チェックシートで要件を整理、契約段階では契約チェックシートで法的事項を確認します。
継続的な見直し
運用開始後も定期的にチェックシートを活用してリスク状況を再評価し、必要に応じて対策を見直します。
関係者間での共有
チェックシートの結果は関係者間で共有し、共通認識の形成とリスク対策の徹底を図ります。
今後の進め方と展望
ガイドラインの継続的改善と政府AI活用の将来像
今後の取り組み
-
ガイドラインの随時見直しAI技術の急速な発展や国際的な動向を踏まえ、ガイドラインの内容を定期的に見直し・更新します。
-
画像・動画等生成AIの来歴証明導入検討テキスト以外の生成AIについても、来歴証明技術の導入を検討し、適用範囲の拡大を図ります。
-
政府全体での生成AIシステム最適化データ連携、共同利用等により、政府全体でのAI活用の効率化と標準化を推進します。
行政の進化と革新に向けて
本ガイドラインは、生成AIの安心・安全な利活用と行政サービスの向上を両立させる画期的な取り組みです。技術の急速な発展に対応しながら、国民の信頼を維持し、より良い行政サービスの提供を目指します。
政府職員の皆様には、本ガイドラインを活用して積極的なAI活用に取り組んでいただき、関連事業者の皆様には、政府の方針を理解した上で、安全で効果的なソリューションの提供をお願いいたします。
安全性の確保
リスク評価と適切な対策により、国民の信頼を維持しながらAI活用を推進
効率性の向上
業務効率化と行政サービスの質的向上を同時に実現
官民連携の促進
明確なガイドラインにより、官民が連携したAI活用の推進
参考情報
関連資料とリンク集
関連資料
-
「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」本文PDF
-
英語版・概要版等の関連資料デジタル庁ウェブサイトにて順次公開予定
-
AI事業者ガイドライン総務省・経済産業省が策定した「AI事業者ガイドライン」も併せて参照
政府AI活用の新時代に向けて
生成AI調達・利活用ガイドラインの策定により、政府のAI活用が新たな段階に入ります。 安全で効果的なAI導入・運用について、専門家と一緒に検討してみませんか?